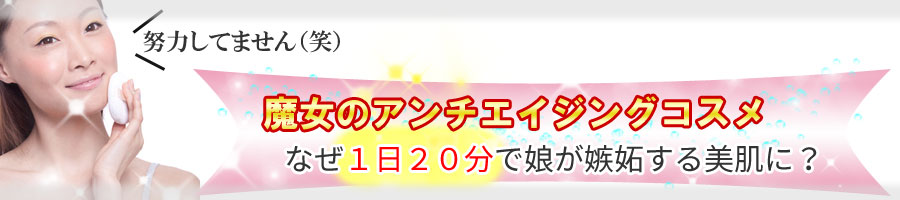
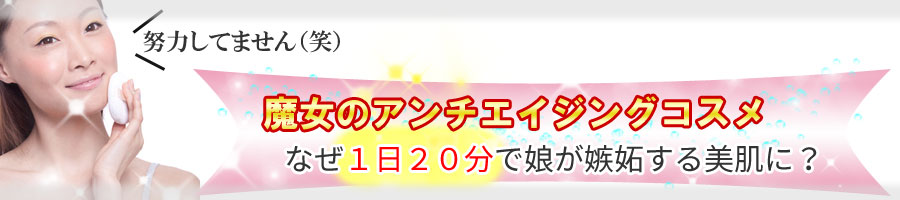
骨密度測定費用の詳細
骨密度測定費用の保険適用条件と負担額

体重計 AI×体組成計【プロスポーツチームにも導入】 スマホ連動 体組成計 INFIELD ブラック
骨密度測定は条件を満たせば健康保険が適用されます。50歳以上の女性、65歳以上の男性、ステロイド服用歴がある方、体重減少や骨折歴がある方は保険適用対象となります。保険適用時のDEXA法による腰椎・大腿骨測定の費用は、1割負担で450円〜720円、3割負担で1,350円〜2,200円程度です。
参考)骨密度検査はどこで受けられる? 費用相場、結果数値の見方、骨…
保険診療では骨塩定量検査として360点(DEXA法腰椎撮影)が設定されており、同日に大腿骨撮影を行う場合は90点の加算があります。これにより実際の医療費は4,500円程度となり、患者の負担割合に応じて支払額が決まります。ただし、検査結果に異常がある場合はレントゲン検査や血液・尿検査が追加され、1割負担で1,200円〜2,000円、3割負担で3,500円〜6,300円程度の追加費用がかかることがあります。
参考)大阪で骨粗鬆症専門の高度な精密検査なら全身型骨密度測定器導入…
保険適用には検査頻度の制限があり、厚生労働省の通知により「同一患者について4ヶ月に1回に限り算定」と定められています。つまり年3回まで(4ヶ月ごと)の頻度制限があり、これを超える場合は自費診療となる可能性があります。
参考)骨密度測定(骨塩定量検査 / Bone Densitomet…
骨密度測定検査方法別の費用比較
骨密度測定の費用は検査方法によって大きく異なります。最も精度が高いDEXA法(デキサ法)は、自費の場合5,000円〜10,000円程度の料金がかかりますが、保険適用時は1,500円〜3,000円程度で受けられます。DEXA法は2種類のX線を用いて腰椎と大腿骨近位部の骨密度を評価し、骨粗鬆症診断ガイドラインでも推奨されている最も信頼性の高い方法です。
参考)https://dai-seikei.com/topics/2025/01/27/what-kind-of-test-is-a-bone-density-test-to-diagnose-osteoporosis/
MD法(エムディー法)は手のひらにアルミ板を置いてレントゲン撮影する方法で、比較的安価に検査できます。QUS法(キューユーエス法)は超音波を用いてかかとや脛の骨密度を測定する方法で、放射線を使わないため妊娠中の方でも安心して受けられ、各自治体の検診では数百円程度で実施されています。
参考)骨粗鬆症の検査費用と内容について解説 - 大阪京橋駅すぐ大阪…
興味深いのは、同じ機械でも施設によって料金設定が異なることです。例えば津山ファミリークリニックでは超音波法の骨密度検査が保険点数80点で設定されており、3割負担でも約240円という非常にリーズナブルな価格で受けられます。このような料金差は検査方法の違いと設備投資コストの差によるものです。
参考)https://smc-seifukai.or.jp/clinic/blog/blog-1353/
骨密度測定の無料検査と自治体検診
費用を抑えて骨密度測定を受ける方法として、自治体の骨粗鬆症検診や薬局・ドラッグストアでの無料測定があります。大阪市では定量的超音波測定法(QUS法)による骨粗鬆症検診を無料で実施しており、検査時間は数分程度で痛みもありません。多くの自治体で500円程度から骨密度検査を受けることができ、住民の健康増進を目的とした取り組みが行われています。
参考)大阪市:骨粗しょう症検診を受けましょう (…href="https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000026192.html" target="_blank">https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000026192.htmlgt;成人の健康href="https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000026192.html" target="_blank">https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000026192.htmlgt;検…
薬局やドラッグストアでも無料の骨密度測定サービスを提供している店舗があります。Vドラッグでは毎月無料健康測定会を実施し、骨密度・血圧・血流の測定を無料で行っています。スギ薬局の一部店舗でも骨強度測定などの無料測定器が設置されており、カラダの気になる部分をチェックできます。
参考)健康相談会
ただし、薬局での測定は簡易的なスクリーニング検査であり、正確な診断には医療機関でのDEXA法による精密検査が必要です。これらの無料検査は骨の健康状態の目安を知るための初期スクリーニングとして活用し、異常が見つかった場合は医療機関での精密検査を受けることが重要です。
骨密度測定の検査頻度と長期的な費用計画
骨密度測定の適切な検査頻度は年齢や骨の状態によって異なり、それに伴って長期的な費用も変わってきます。40代では3年ごと、50-64歳では2年ごと、65歳以上では年1回の検査が推奨されています。特に65歳以上では年間約3%の割合で骨密度が低下するため、定期的なモニタリングが重要です。
骨粗鬆症と診断された患者では6ヶ月ごとの骨密度検査が推奨され、治療効果の判定や経過観察のために定期的な測定が必要です。日本骨粗鬆症学会のガイダンスでは、治療開始時には半年〜1年後に効果判定として測定し、その後は1〜2年おきに測定することを推奨しています。
参考)気軽に受けたい骨粗しょう症の検査 骨折しない毎日を送るために…
長期的な費用を考えると、保険適用の条件を満たす方は定期的に医療機関での検査を受け、それ以外の方は自治体検診や薬局での無料測定を活用するという使い分けが経済的です。例えば40代女性の場合、3年ごとに自治体検診(500円程度)を受け、50歳を過ぎて保険適用になったら医療機関での検査(1,500円程度)に切り替えるといった計画的な受診が効果的です。
骨密度測定検査の独自の新視点と将来展望
最近注目されているのが、AIを活用した既存のレントゲン画像からの骨密度推定技術です。胸部レントゲンやCT検査のHU(ハウンスフィールド単位)値から骨密度を推定する研究が進んでおり、追加の検査費用をかけずに骨の健康状態を評価できる可能性があります。これにより将来的には、定期健診の胸部レントゲンから自動的に骨粗鬆症のリスクを判定できるようになるかもしれません。
参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8446034/
また、家庭用骨密度測定器の技術も向上しており、病院に行かなくても自宅で骨の健康状態をチェックできるデバイスの開発が進んでいます。現在のスマートフォンアプリと連動した簡易測定器も登場しており、継続的な骨の健康管理がより身近になる可能性があります。
さらに興味深いのは、骨密度と筋力や運動能力の相関関係を調べた研究で、短距離走タイムや投球能力から骨密度を予測する試みも行われています。これらの研究が進歩すれば、体力テストの結果から骨の健康状態を推測し、必要な方にのみ精密検査を勧めるという効率的なスクリーニングシステムが構築できるかもしれません。
参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9772019/