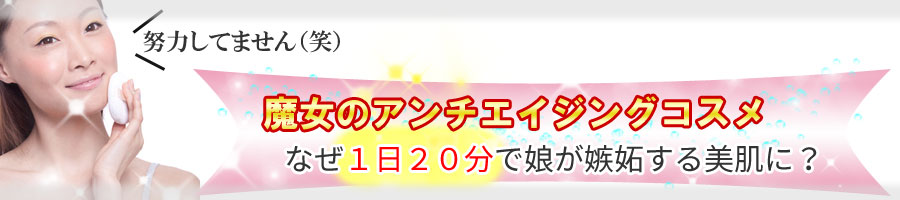
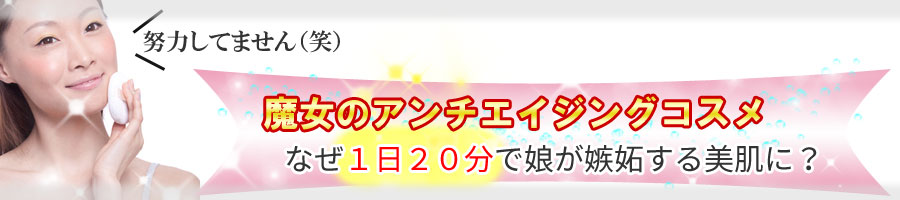
糖尿病診断基準による血糖値判定
糖尿病診断基準の空腹時血糖値判定項目
日本糖尿病学会が定める糖尿病診断基準(2024年版)では、「糖尿病型」の判定に以下の数値が用いられています 。糖尿病診断において最も重要な指標の一つが空腹時血糖値であり、10時間以上絶食後に測定された血糖値が126mg/dL以上の場合に糖尿病型と判定されます 。
参考)糖尿病の診断基準、血糖値の基準値について詳しく解説します!|…
空腹時血糖値の判定区分は段階的に設定されており、正常型は110mg/dL未満、境界型は110~125mg/dL、そして糖尿病型は126mg/dL以上となっています 。さらに細かく分類すると、99mg/dL以下を正常値、100~109mg/dLを正常高値(糖尿病の発症リスクが高い状態)と定義しています 。
参考)https://kmc-bunko.com/%E7%97%85%E6%B0%97%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85%E3%81%AE%E8%A8%BA%E6%96%AD%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%80%9C%E8%A1%80%E7%B3%96%E5%80%A4%E3%81%A8hba1c/
糖尿病診断では単一の検査結果だけでなく、複数回の測定により高血糖を確認することが必須とされています 。これは、様々な病態で一過性に高血糖をきたすことがあるため、それらを区別するための重要な診断プロセスです 。
参考)https://www.jds.or.jp/uploads/files/publications/gl2024/01.pdf
糖尿病診断基準のHbA1c基準値と特徴
HbA1c(ヘモグロビンA1c)は糖尿病診断基準において中核的な役割を果たしており、6.5%以上で糖尿病型と判定されます 。この検査の最大の特徴は、過去1~2ヶ月間の平均血糖値を反映することで、一時的な血糖変動に左右されない安定した指標となる点です 。
参考)糖尿病の診断基準 − 糖尿病の診断基準(空腹時血糖値・フロー…
HbA1c値による判定区分は、5.6%未満が正常範囲、5.6~6.4%が糖尿病予備群の可能性、6.5%以上が糖尿病型とされています 。しかし、HbA1cのみでの糖尿病診断には制限があり、赤血球の寿命が短くなる出血などの影響で数値が低く出る場合があるため、血糖値との組み合わせでの診断が推奨されています 。
参考)糖尿病の診断基準とは?最新ガイドラインに基づく明確な見極めポ…
2010年の診断基準改訂により、HbA1cが従来の補助的診断基準からより上位の診断基準として位置づけられ、血糖値とHbA1cの両方が糖尿病型を示せば初回検査だけで糖尿病と診断できるようになりました 。この変更により、1回の検査で糖尿病と診断できる症例が大幅に増加し、早期診断・早期介入が促進されています 。
参考)https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001f0mk-att/2r9852000001f0tj.pdf
糖尿病診断基準の負荷試験による判定方法
75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)は、糖尿病診断において欠かせない検査の一つで、ブドウ糖75gを摂取後2時間の血糖値が200mg/dL以上で糖尿病型と判定されます 。この検査は、空腹時血糖値が正常範囲でも食後に血糖値が異常に上昇する隠れた糖尿病を発見するために重要な役割を果たしています 。
負荷試験における判定基準は段階的に設定されており、2時間値が139mg/dL以下で正常型、140~199mg/dLで境界型(耐糖能異常)、200mg/dL以上で糖尿病型となります 。随時血糖値についても同様に、食事の時間に関係なく測定した血糖値が200mg/dL以上で糖尿病型と判定されます 。
参考)健康診断で「血糖高値」や「境界型」と言われたら?
負荷試験は特に、空腹時血糖値やHbA1cが境界領域にある場合の精査で推奨されており、糖尿病の疑いが否定できない患者において確定診断のための重要な検査となっています 。検査前には糖質制限しない食事を3日以上続ける必要があり、適切な準備が正確な診断につながります 。
参考)糖尿病予備群といわれたら
糖尿病診断基準の境界型判定と症状評価
境界型糖尿病(糖尿病予備軍)は、明確な糖尿病型ではないものの正常から逸脱している状態を指し、空腹時血糖値110~125mg/dL、HbA1c6.0~6.4%、75g負荷試験2時間値140~199mg/dLのいずれかを満たす場合に診断されます 。境界型の段階では多くの場合自覚症状がなく、健康診断で初めて発見されることがほとんどです 。
参考)境界型糖尿病について解説|新宿で糖尿病治療ならヒロオカクリニ…
糖尿病の典型的症状には口渇、多飲、多尿、体重減少があり、これらの症状が存在する場合は1回の検査結果でも糖尿病と診断することが可能です 。また、確実な糖尿病網膜症の存在も同様に、初回検査での診断を可能にする重要な所見とされています 。
境界型から糖尿病への進行を防ぐため、この段階での生活習慣改善が極めて重要です 。「将来糖尿病を発症するリスクが高い」グループ(HbA1c5.6~6.0%、空腹時血糖値100~110mg/dL未満)も存在し、特に高血圧、脂質異常症、肥満を合併する場合は積極的な検査と管理が推奨されています 。
参考)【糖尿病】2025年 糖尿病診療アップデートのポイント
糖尿病診断基準の肥満指標と新たな診断アプローチ
糖尿病診断において肥満の評価は重要な要素であり、BMI(Body Mass Index)25以上を肥満と定義し、糖尿病発症リスクの評価に活用されています 。特にBMI25以上で糖尿病・高血圧症・脂質異常症のいずれかを有する場合、または BMI35以上の高度肥満の場合は、積極的な糖尿病スクリーニングが推奨されています 。
参考)肥満に伴う糖尿病治療|恋ヶ窪内科クリニック|国分寺・恋ヶ窪の…
2025年版の米国糖尿病学会(ADA)ガイドラインでは、糖尿病検査開始年齢の引き下げが盛り込まれ、リスク要因のない人でも35歳から定期的な糖尿病検査の開始が推奨されています 。これは糖尿病の早期発見と予防を目的とした重要な変更です 。
現在の診断システムでは、過去に糖尿病と診断された証拠がある場合、現時点の血糖値が糖尿病型の基準値以下であっても糖尿病として対応することが定められています 。また、最新の診断基準では血糖値とHbA1cの同時測定が推奨されており、より確実な診断精度の向上が図られています 。
カラダのものさし 血糖スパイク検査「スパイクチェック」 1個
