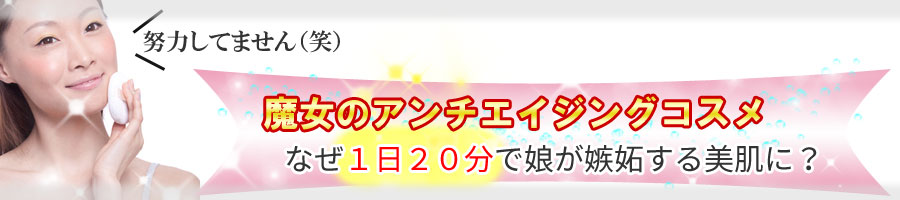
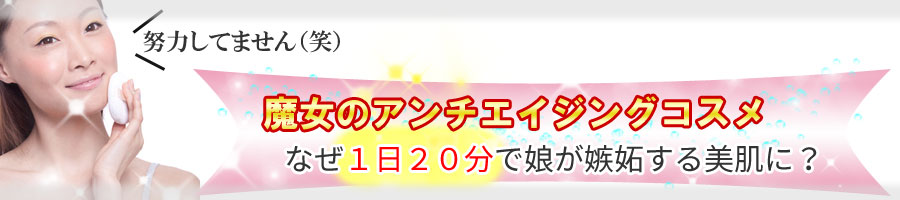
骨粗しょう症とは
骨粗しょう症は、骨密度の低下と骨質の劣化により骨強度が低下し、骨折しやすくなる疾患です 。世界保健機関(WHO)では「低骨量と骨組織の微細構造の異常を特徴とし、骨の脆弱性が増大し、骨折の危険性が増大する疾患」と定義されています 。
参考)href="https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/osteoporosis.html" target="_blank">https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/osteoporosis.htmlamp;#x300C;href="https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/osteoporosis.html" target="_blank">https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/osteoporosis.htmlamp;#x9AA8;href="https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/osteoporosis.html" target="_blank">https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/osteoporosis.htmlamp;#x7C97;href="https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/osteoporosis.html" target="_blank">https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/osteoporosis.htmlamp;#x9B0…
日本では男性300万人、女性980万人、合計1,280万人の患者がいると推計されており、高齢化に伴って患者数は増加傾向にあります 。骨粗しょう症は「21世紀のサイレント病気」と呼ばれ、その重篤性、慢性経過、進行性により公衆衛生上のリスクとなっています 。
参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9408932/
骨は生きており、新たに作られること(骨形成)と溶かして壊されること(骨吸収)を繰り返していますが、骨粗しょう症ではこのバランスが崩れ、骨吸収が骨形成を上回ることで骨がスカスカになってきます 。特に女性では閉経後に女性ホルモンの減少により急激に骨密度が低下するため、注意が必要です 。
参考)女性ホルモンの減少が引き起こす「更年期障害」と「骨粗しょう症…
骨粗しょう症の症状とは
👤 初期症状の特徴
骨粗しょう症の初期段階では、痛みなどの自覚症状がほとんどありません 。しかし病気が進行すると、転倒や軽い動作でも骨折しやすくなり、以下のような症状が現れます 。
参考)骨粗しょう症 - 08. 骨、関節、筋肉の病気 - MSDマ…
📍 主な症状
- 背中や腰の鈍い痛みが続く
- 身長が縮む・姿勢が悪くなる(円背)
- わずかな衝撃でも骨折しやすくなる
特に脊椎圧迫骨折では「体動時腰痛」と呼ばれる特徴的な痛みが現れ、体を動かすときに腰や背中に痛みを感じるようになります 。骨粗しょう症患者の8割以上で何らかの腰背部痛があることが調査で明らかになっています 。
参考)【どんな痛み?】骨粗鬆症の症状とは|セルフチェック方法や受診…
骨粗しょう症の原因と女性ホルモン
🔬 骨代謝メカニズム
骨粗しょう症の主な原因は、骨吸収と骨形成のバランスが崩れることです。加齢、エストロゲンの不足、ビタミンDやカルシウムの摂取不足、特定の疾患などにより、骨密度や骨強度を維持する成分の量が減少します 。
👩⚕️ 女性ホルモンの影響
女性ホルモンのエストロゲンには、骨を作る細胞(骨芽細胞)の働きを助け、骨を壊す細胞(破骨細胞)の働きを抑える重要な作用があります 。閉経によりエストロゲンの分泌が急激に減少すると、骨を作る力が弱まり、逆に壊す力が強まってしまいます 。
参考)女性ホルモンが減少すると骨がもろくなる!?骨粗しょう症を防ぐ…
📊 閉経後の骨密度変化
50歳前後の更年期を境に骨密度が急激に減少し、もともと男性に比べて骨量が少ない女性では、加齢による影響と更年期のエストロゲン減少が重なって、50代以降に骨粗しょう症の発症が急増します 。
骨粗しょう症の検査と診断方法
🔍 骨密度検査(DEXA法)
骨粗しょう症の診断で最も重要なのが骨密度検査です。DEXA(デキサ)法では、2種類の異なるX線エネルギーを用いて骨と軟部組織を区別し、腰椎や大腿骨の骨密度を正確に測定します 。被ばく量が比較的少なく、短時間で測定できる利点があります 。
参考)骨粗鬆症の早期発見と予防に必要な検査について - 足立慶友整…
📈 診断基準
測定した骨密度を20~44歳の若年層の平均値(YAM)と比較し、YAMの70%以下の場合に骨粗しょう症と診断されます 。YAMの70~80%の範囲では骨粗しょう症のリスクが高い状態とされ、持病なども考慮して治療方針を決定します 。
参考)骨粗鬆症の検査・治療|柏市南柏のKENカルディオクリニック柏…
🩸 血液検査
骨代謝マーカーを測定する血液検査も重要な診断材料となります 。これにより骨の新陳代謝の状況を把握し、より詳細な病状評価が可能になります。早期発見のためには定期的な検査・検診が重要で、症状が現れる前に骨の状態を確認することで、適切な治療により骨折リスクを下げることができます 。
参考)骨粗しょう症の早期発見は定期的な検査・検診から - 骨検 b…
骨粗しょう症の治療薬と方法
💊 ビスホスホネート製剤
骨粗しょう症治療の中心となるのがビスホスホネート製剤です。この薬剤は破骨細胞に取り込まれ、骨吸収を抑制し骨密度を増加させます 。アレンドロン酸(ボナロン)、リセドロン酸(アクトネル)、ミノドロン酸(リカルボン)などがあり、内服薬では毎日、週1回、4週に1回の服用間隔があります 。
参考)骨粗しょう症の治療薬 ビスホスホネート製剤のお話
⚠️ 注意事項
ビスホスホネート製剤の内服薬は腸管からの吸収が悪いため、「起床後すぐに服用し、その後30分は水以外飲食してはいけない」という厳格な服用制限があります 。また、稀ではありますが顎骨壊死という副作用のリスクがあるため、治療開始前の歯科受診と口腔ケアが重要です 。
参考)一般財団法人 脳神経疾患研究所 総合南東北病院【地域がん診療…
🏥 その他の治療選択肢
ビスホスホネート製剤以外にも、選択的エストロゲン受容体モジュレーター(SERM)などの骨吸収抑制薬や、新しい骨を作る骨形成促進薬があります 。注射や点滴による投与方法もあり、4週に1回から年1回まで様々な投与間隔が選択できます 。
骨粗しょう症に良い食べ物と避けるべき食品
🥛 カルシウム豊富な食品
骨の主成分であるカルシウムは毎日700mgの摂取が推奨されます 。乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)、小魚(イワシ、ししゃも、桜えび)、大豆製品(豆腐、納豆、豆乳)、海藻類(わかめ、ひじき、昆布)を積極的に摂取しましょう 。
参考)【骨粗しょう症】避けたい食品とおすすめの食べ物 - 田所整形…
🐟 ビタミンDとビタミンK
カルシウムの吸収を助けるビタミンDは魚類(サケ、イワシ、マグロ)やキノコ類(干しシイタケ、マイタケ)に豊富に含まれています 。カルシウムの骨への沈着を促進するビタミンKは納豆や緑黄色野菜から摂取できます 。
参考)骨粗鬆症の予防・治療における栄養・食事のポイント - 骨検 …
❌ 避けるべき食品
以下の食品は骨の健康に悪影響を与える可能性があります :
参考)骨粗鬆症で食べてはいけないものはある?骨を強くする食べ物も解…
- リンを多く含む食品(インスタント麺、スナック菓子、清涼飲料水の添加物、加工肉)
- 過剰な食塩
- カフェイン
- アルコール
リンはカルシウムと結合して体外に排出してしまう性質があるため、リンを多く含む食品ばかりの食事は避けることが重要です 。バランスの良い食事を基本として、適切なエネルギーやたんぱく質の摂取も骨の健康維持には欠かせません 。
骨粗しょう症を防ぐ 強い骨のつくり方 (POWER MOOK)
